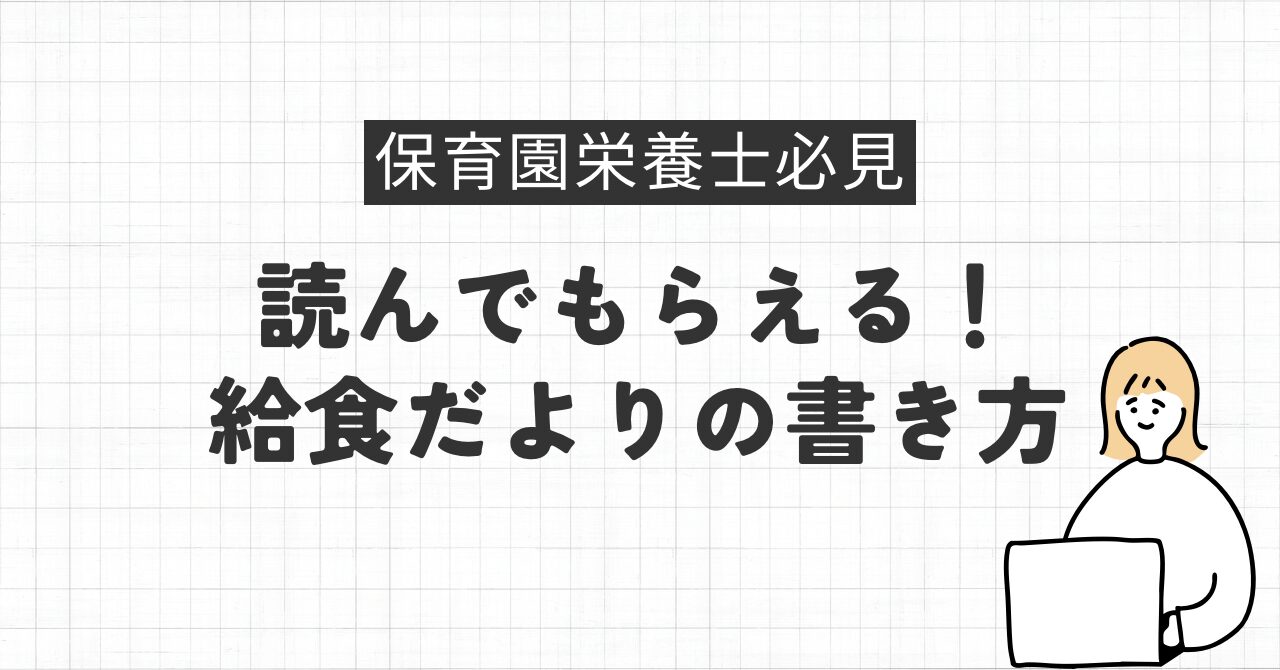毎月の給食だより、読んでもらえてますか?
保育園で働く栄養士の皆さま、毎日忙しいですよね。本当にお疲れ様です。
午前中は厨房で調理、クラス回り。
午後も場合によっては洗い物や調理。
午後おやつの検食を出したら、必死に事務仕事をして、あっという間に夕方になります。

ああ、今月も月末だ。給食だよりを書かないと間に合わない!

もう時間がないから、これでいいか!
と、給食だよりを書くことが「やっつけ仕事」になってませんか?
ネットで「◯月給食だより 保育園」などというキーワードで検索すると、たくさんの給食だよりが見られます。
中には「読んでもらえない給食だより」・・・あまり上手ではない給食だよりも数多くヒットします。
・おたより集からそのままコピーしたもの
・子どもたちの様子がひと言も書かれていないもの
これらは、「給食だより」とは言えません。
時間がない中でも、読んでもらえる給食だよりを書くことはできます。
今回は、給食だよりを書くコツをお伝えします!
読んでもらえる!給食だよりを書くコツ5つ
忙しい中で作る給食だより、保護者にきちんと読んでもらいたいですよね。
読んでもらえる、上手な書き方のコツをお伝えします。
たったの5つのことを意識するだけで、格段に読みやすい給食だよりになるはずですよ!
①文章の1文を短くする
例えば、「おうちでお手伝い」をテーマにしたこの文章。
楽しくお手伝いする中で、食への興味が育っていくので、お手伝いをしてくれた時には「ありがとう」と伝えてあげましょう。
この文章を2つに分けたら、どうでしょうか。
楽しくお手伝いする中で、食への興味が育っていきます。
お手伝いしてくれた時には「ありがとう」と伝えてあげましょう。
1文を短く簡潔にするだけで、伝わりやすい文章になったことが感じられたかと思います。
区切ることができるなら、文章を区切って短くすること。
これが1つ目のポイントです。
②写真と共に、子どもたちの様子(エピソード)を書く
保護者が一番知りたいのは、栄養の話でもなくて、我が子のこと。
我が子がどんな食事をして、どんな風に過ごしているのか、写真があると必ず見ます。
クッキングをしたり、野菜を収穫したりした時は、写真を撮っておくと良いですよ。
園によっては子どもの顔が写っていると掲載NG、ということもありますので、園内のルールはしっかり確認しておきましょう。
また、最近はICT化が進み、献立表や給食だよりをアプリで配信する園も増えてきたと思います。
スマートフォンで読むには、カラーの方が目をひきやすいです。
あえて色を取り入れたり、写真を入れると、興味を持ってもらいやすいですよ。
③余白を残す
時々、余白がほとんどなく、文字がびっしり!という給食だよりを見かけます。
最近はスマートフォンで読むことも考慮すると、ある程度の余白があった方が見やすいです。
イラストや写真、飾り枠などを効果的に入れて、余白も大切にしましょう。
ポイント1つ目の、1文を短くすることを意識すると、自然と文字数は少なくなるはずです。
また、イラストを使用する際に気をつけたいことが、「著作権」です。
フリーイラストだと思っていたら、実は著作権があり、裁判になって数十万円を支払った・・・などという事例も発生しています。
必ず著作権フリーのものでも、使用条件など一度は確認しましょう。
よく分からない場合は、おたより集を購入して、付属イラストを使用することが最も安全です。
④1日おいて読み返す、または他の人に読んでもらう
そんなこと?と思われるかもしれませんが、この方法がとても効果的です。
時間を置いて改めて読むと、相手の立場(保護者目線)で読む事ができます。
さらに、誤字脱字だけでなく、「この言い回しが変だな」など気が付く事ができます。
もし、他の職員に読んでもらえるなら、誰でも良いので読んでもらいましょう。
「この部分ってどういう意味?」など、自分は分かりやすいと思って書いたことでも、初めて読む人には伝わりにくいこともあります。
自分ひとりで完結していたら気づくことのできなかった事ですよね。
毎月この方法を取り入れれば、文章を書くスキルがどんどん上達していくはずです!
⑤レシピ紹介は、相手に寄り添った書き方をする
毎月の給食だよりで、旬の食材を使ったレシピを紹介する場合もあります。
その場合は、相手に寄り添った書き方を意識しましょう。
★作りやすい分量で表記する
幼児1人分のレシピだと、家族分作るのに4倍や5倍に直さないといけないため、まず作りません。
オススメは幼児5人分で表記すること。
幼児5人分であれば、大人2人+子ども1人、3人家族のイメージです。
★材料の分量は、大さじや小さじ表記にする
g表記よりも、大さじ・小さじ表記の方が「作ってみよう」のハードルは下がります。
いちいち重さを計るのは面倒ですし、保育園に通っているということはママも働いています。
なるべく簡単に作れるように、レシピを書けるとよいですね!
最後に
「毎月の給食だよりが苦痛だ」と思う保育園栄養士の役に立てたらと、この記事を書かせていただきました。
もし、身近に先輩栄養士や同僚がいるなら、先輩方の給食だよりをたくさん読ませてもらうと良いですよ。
そして上手な人を見つけられると、さらにご自身の成長につながると思います。
私は運良く、給食だよりを書く事が上手な先輩に出会う事ができました。
「この人みたいに上手に書けるようになりたい」という目標ができ、そこから「伝わる文章の書き方」について勉強するようになりました。
今はこちらの本を読んでいるところです。
おたより集は、絵が可愛いと思うものを購入したら良いです。
できれば、文例は編集して、自分の言葉にできるものが良いですね。
参考までにリンクを貼っておきます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
毎月の給食だよりについても、後々記事にしたいと思います。
また別記事でもお会いしましょう!